はじめに|AIとブロックチェーンの融合が生んだ新時代のレイヤー1「0G」

 クリプト王子
クリプト王子ブロックチェーンとAIの融合が加速するなか、注目を集めているのが世界初のAI特化型レイヤー1「0G(Zero Gravity)」です。
ストレージや計算処理をオンチェーン化し、AIの学習や推論を直接ブロックチェーン上で実行できる点で、次世代インフラとして期待されています。
本記事では、0Gの仕組み、資金調達、トークン情報、さらには上場状況やユースケースまで詳しく解説します。
0G(Zero Gravity)とは?
とは?-1024x683.png)
とは?-1024x683.png)
0Gは「AI × ブロックチェーン」をコンセプトに掲げる新興プロジェクトです。
大きな特徴はモジュラー型アーキテクチャで、以下の4つの独立サービスを組み合わせることでAIワークロードを効率的に処理します。
- Storage:水平分割された高速ストレージ
- Compute:PoRA(Proof of Random Access)による分散AI処理
- Chain:EVM互換チェーンでのスマートコントラクト実行
- Data Availability:VRFを用いたデータの可用性保証
既存のEthereumやPolygon上のdAppも追加開発なしで、0Gの計算資源やストレージを利用可能です。
開発組織と資金調達
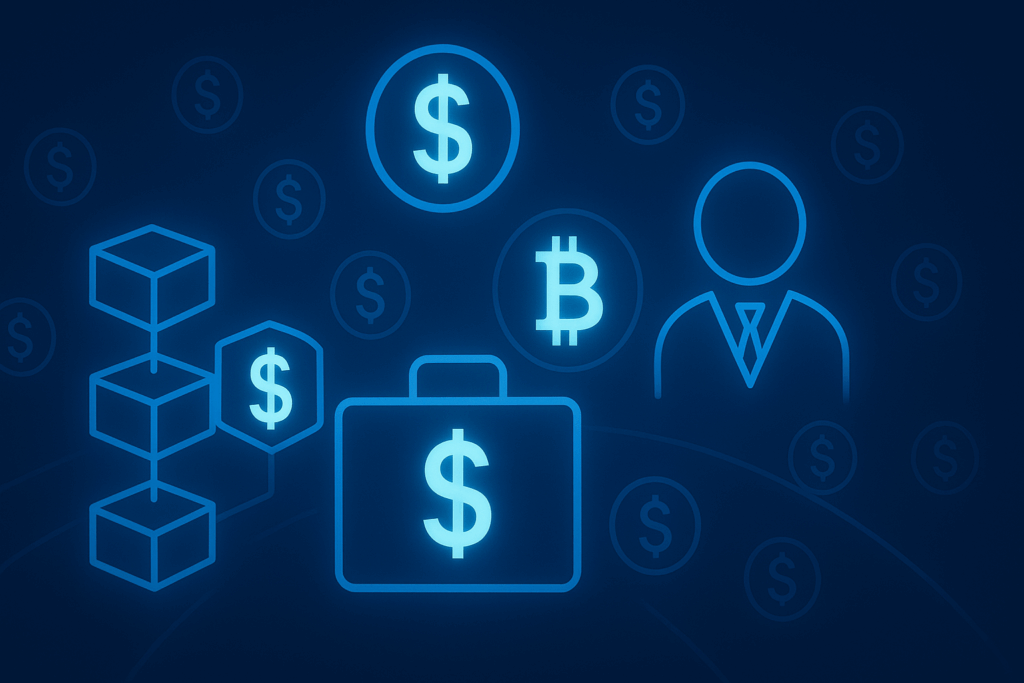
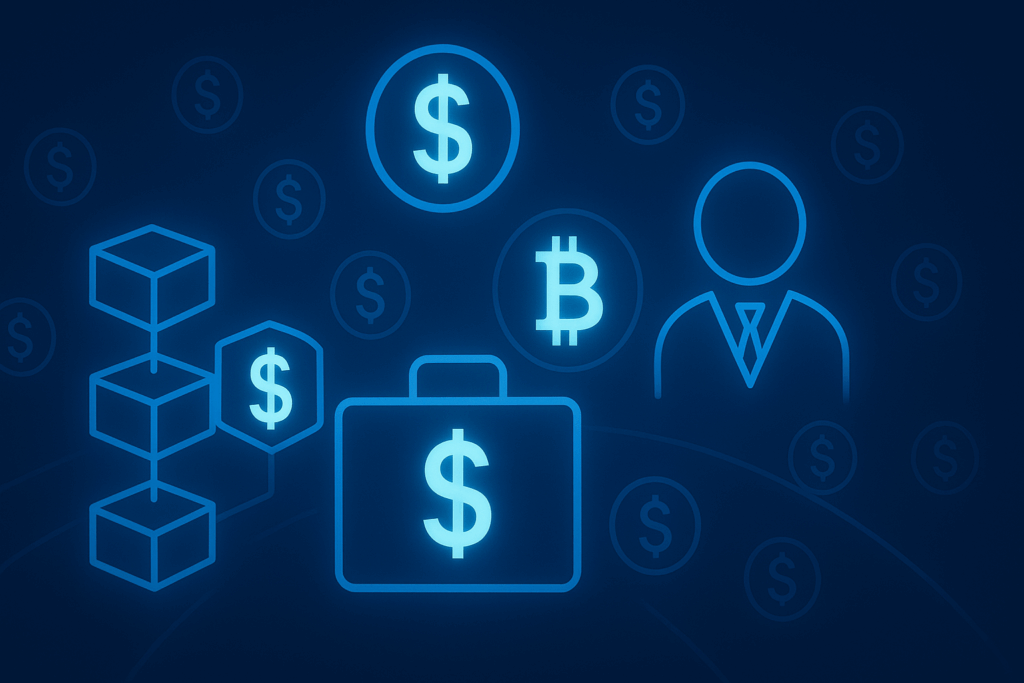
開発は米国拠点の 0G Labs が担っています。
2024年11月にはHack VC、Samsung Next、Animoca Brandsなどから 4,000万ドルのシード資金 を調達。
さらに 2億5,000万ドル規模の流動性枠 を確保し、累計で 約2億9,000万ドル に達しました。
このスピードと規模はAIインフラ領域としても異例で、プロジェクトの注目度を物語っています。
モジュラー設計の全体像
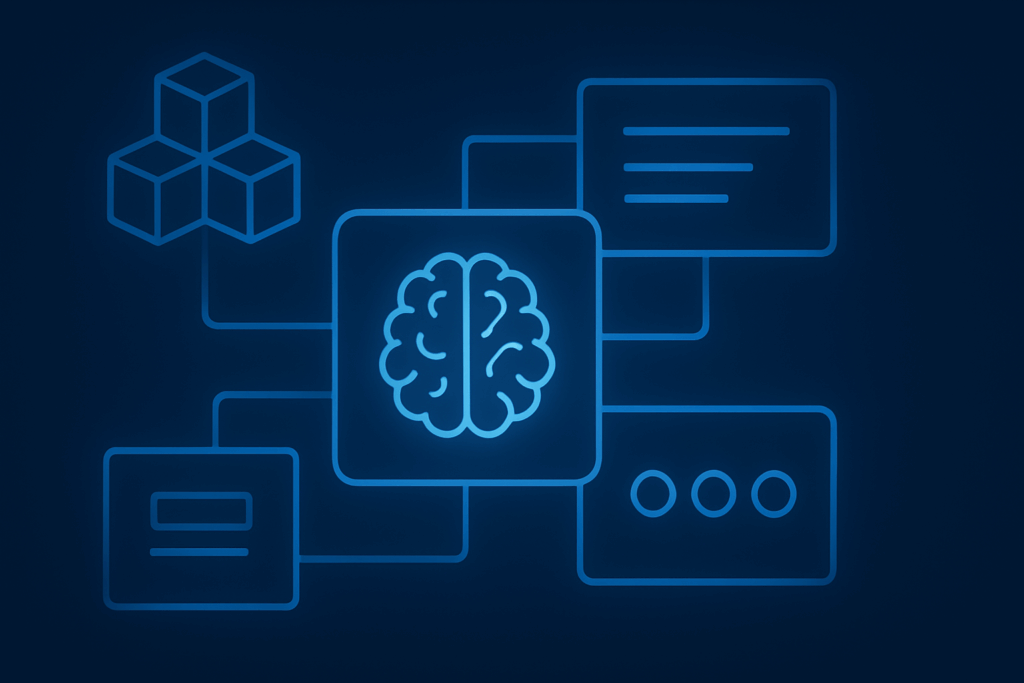
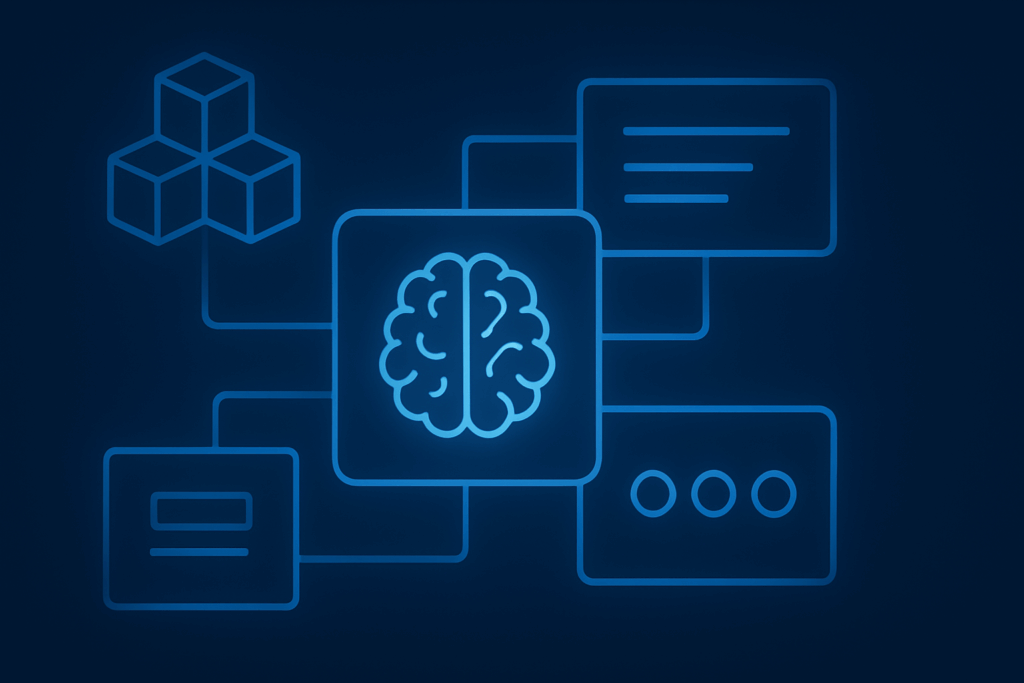
0Gの強みは「必要な機能だけを選んで利用できる」柔軟な設計です。
- Storage:大容量データを即座に保存・取得可能
- Compute:分散されたGPUでAI推論・学習を実行
- Chain:EthereumベースのEVM互換環境
- Data Availability:複数ノード署名によるデータ真正性保証
これらはAPIを通じて呼び出せるため、開発者にとって導入ハードルが低い点も魅力です。
0Gチェーン:EVM互換の新基盤


0GチェーンはEthereumクライアントを改良したレイヤー1です。
EigenLayerを利用したShared Stakingモデルにより、セキュリティを高めています。
バリデータ報酬はEthereum側と0G側で連動し、二重会計のリスクを防ぎつつ効率的な運用を可能にしています。
ストレージとデータ可用性
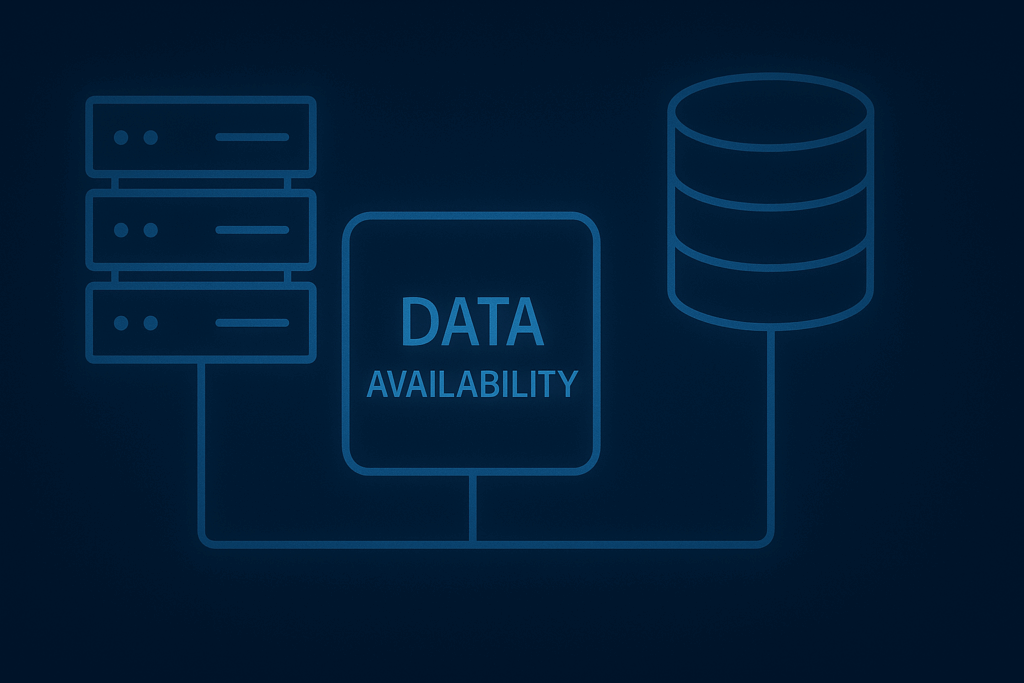
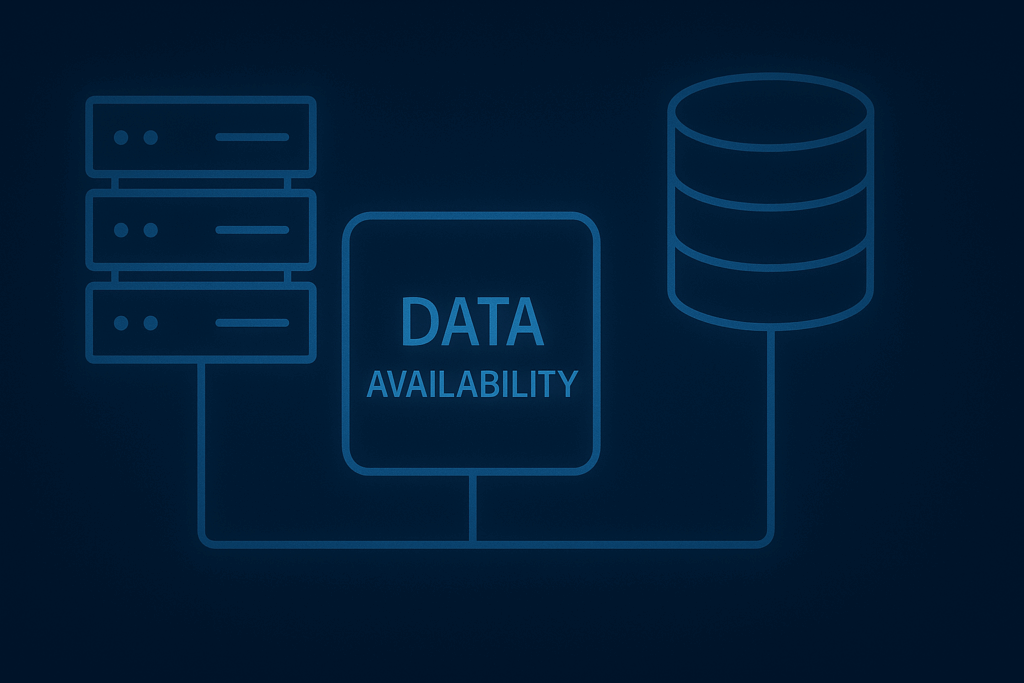
- ストレージ層:ERC-20トークン「0G」がガスとして利用され、データ保存ノードはPoRAに基づき報酬を獲得。
- データ可用性層:ランダム選出ノードの過半数署名により検証を行い、オフチェーン証明を不要化。
これによりスケーラビリティと信頼性を両立しています。
AI統合とComputeサービス
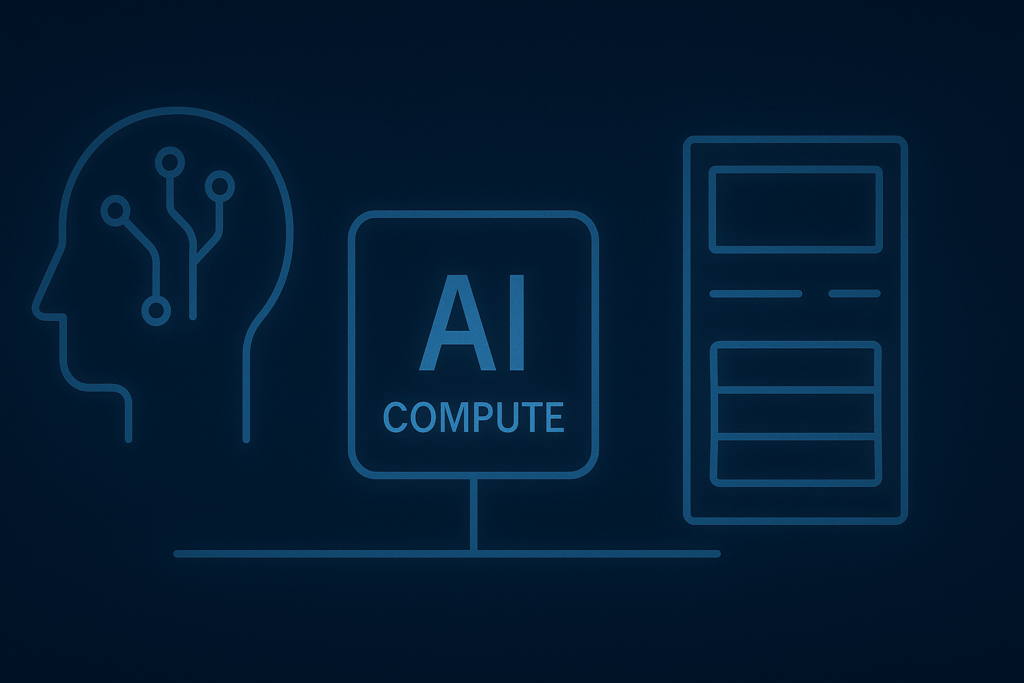
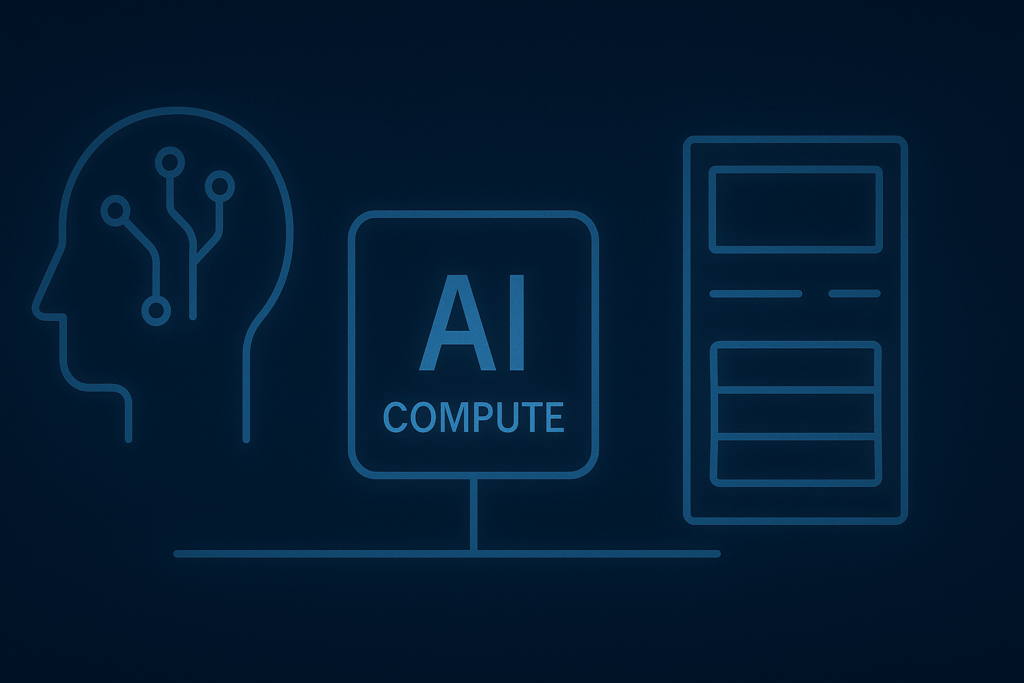
AI推論や学習のようなGPUを必要とするタスクは、Compute層が分散的に処理します。
SDK(TypeScript/Go)を利用することで、モデルのアップロードやファインチューニング、推論呼び出しまでをオンチェーンで実行可能です。
支払いはスマートコントラクトで自動化されており、透明性の高い取引を実現します。
トークン「0G」の概要
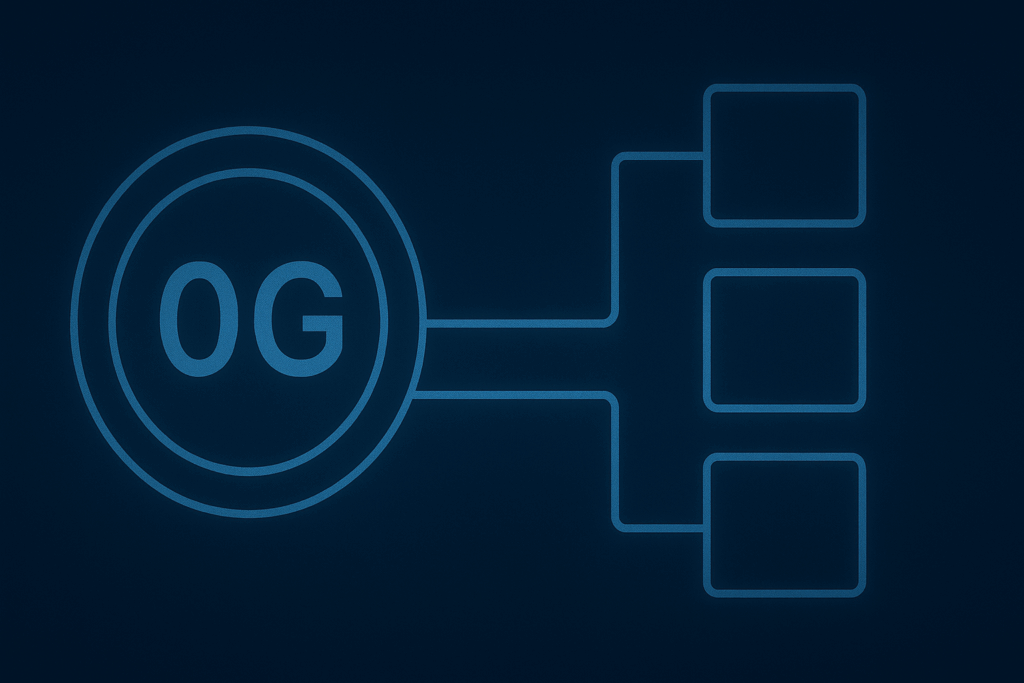
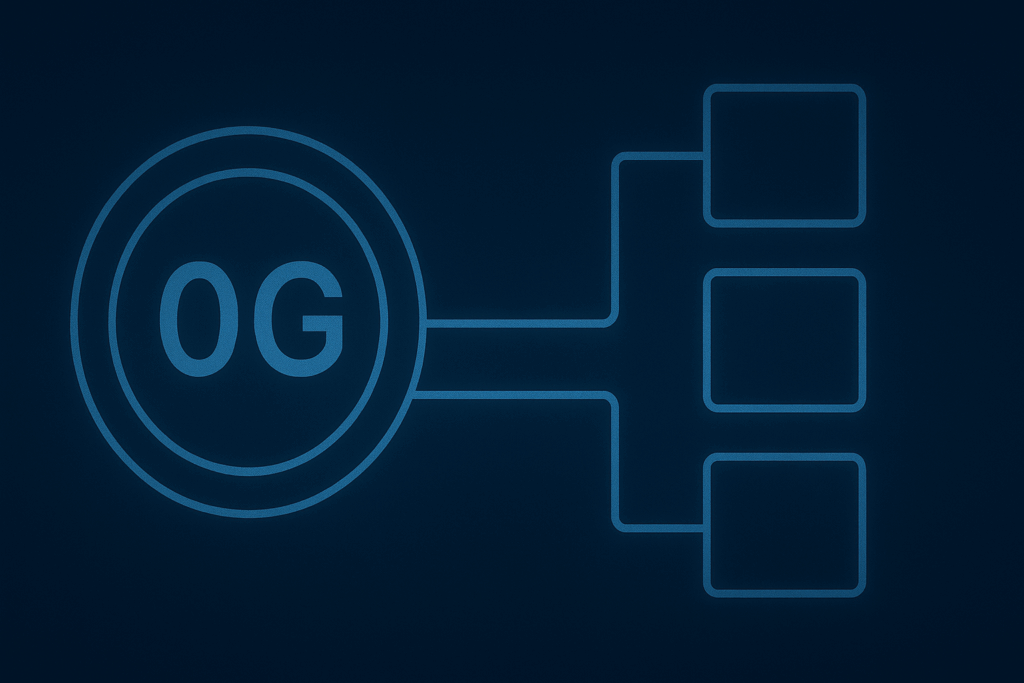
- 総供給量:10億枚
- インフレ率:年3.5%(上限なし)
- 用途:ガス、報酬、ガバナンス投票、ステーキング
- 初期配分:エコシステム22%、チーム15%、投資家20%、コミュニティ43%
トークン設計はネットワーク保護とコミュニティ拡大の両立を意識しています。
上場状況
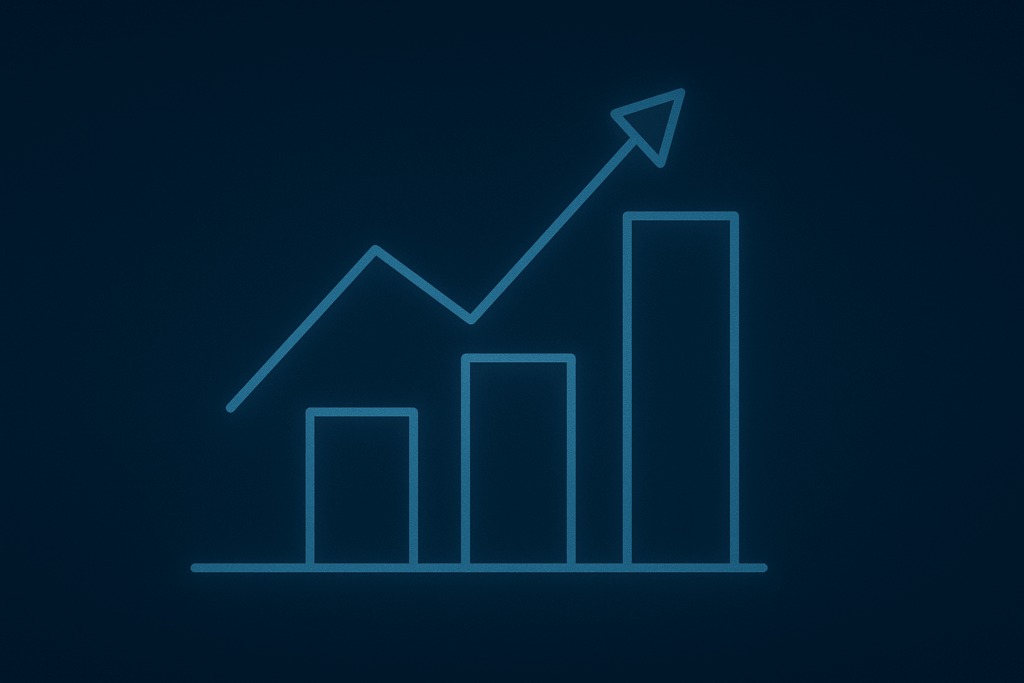
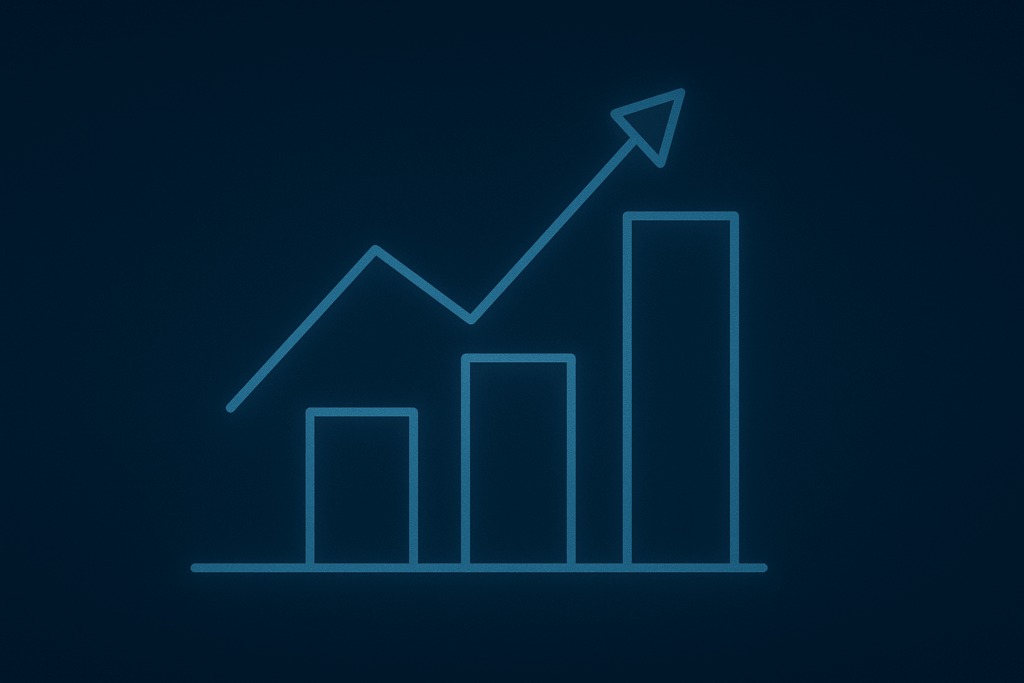
- Binance(2025年9月22日)
上場価格4.465ドル。USDT/USDC/BNB/FDUSD/TRYの5ペアで取引開始。マージン・先物も同日解禁。
- Kraken
同日に現物取引を開始。USD・EUR建てがサポートされました。
ユースケース:iNFTとAIverse


0Gは iNFT(Intelligent NFT) という新しい規格を提案。
AIエージェントをNFTに格納し、所有者は推論能力を含めて取引できます。
さらに2025年9月には、iNFT専用マーケット「AIverse」がテストネットで公開されました。
リスクと課題
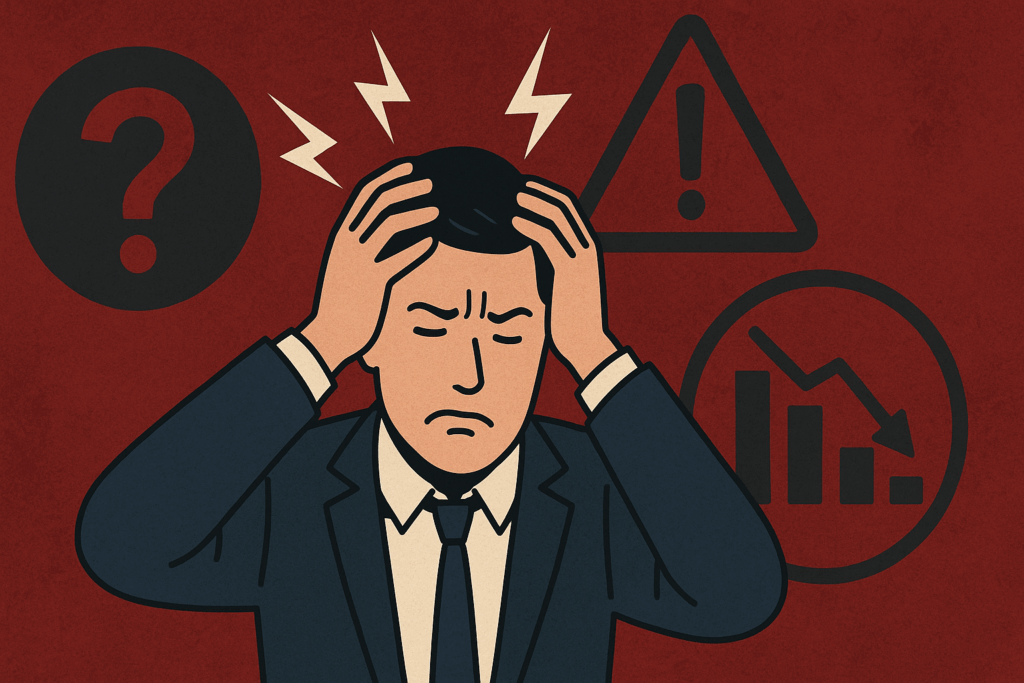
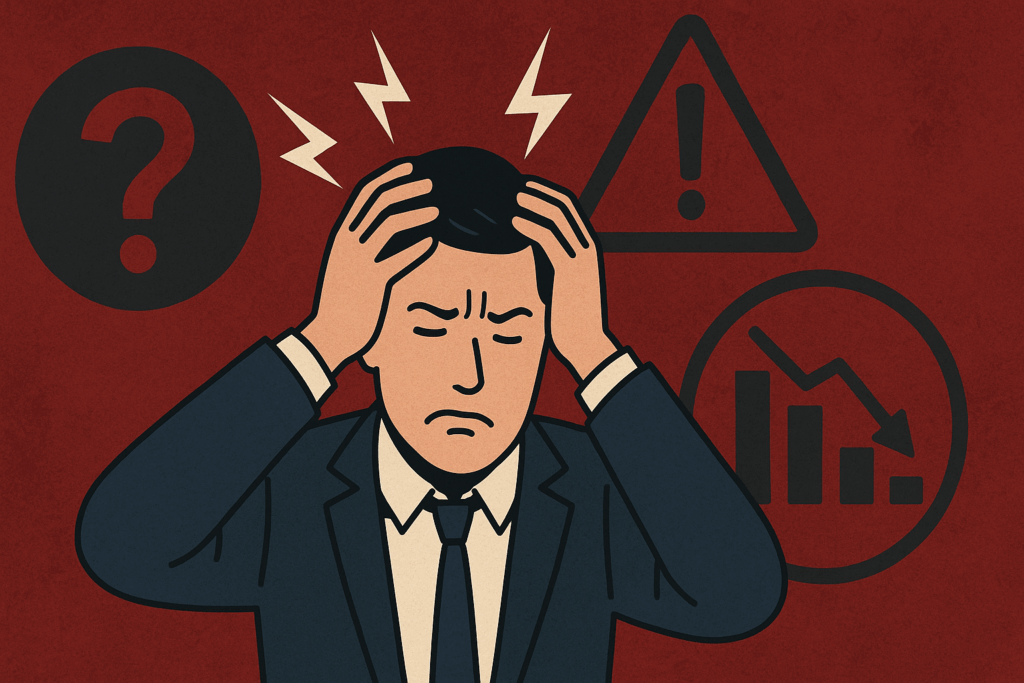
- 競合:EthereumやSolanaなど既存L1との開発者獲得競争
- 規制:AI・暗号資産双方で不透明な法制度
- 流動性:新規銘柄特有の市場深度不足
- 技術的難易度:4層構造による監査コスト増
これらの課題は公式ブログでも明示されており、投資家は注意が必要です。
ロードマップ
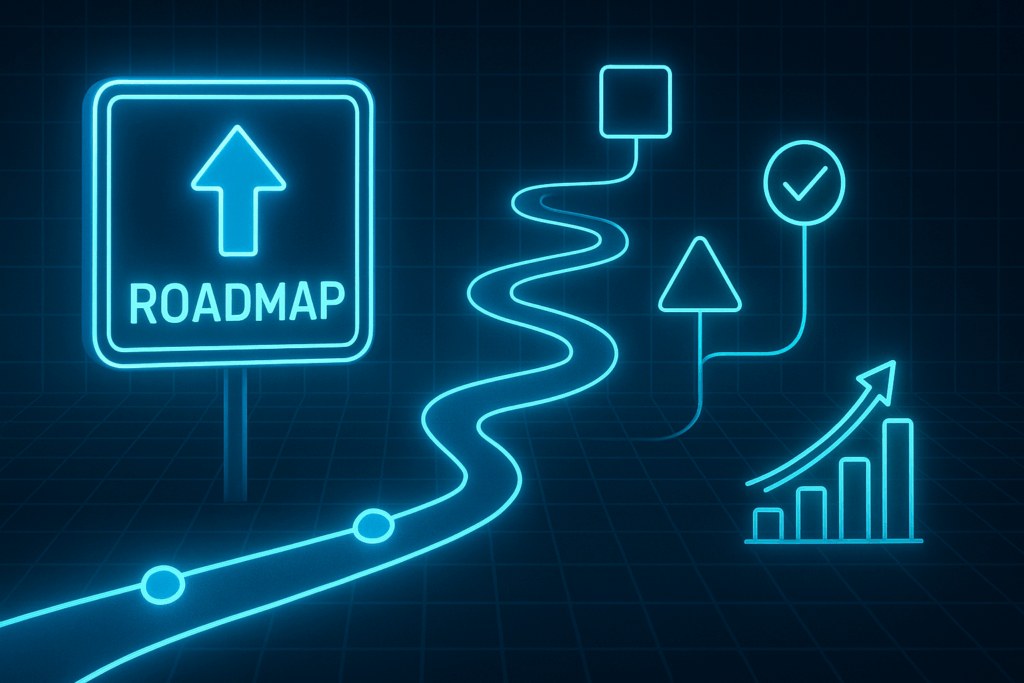
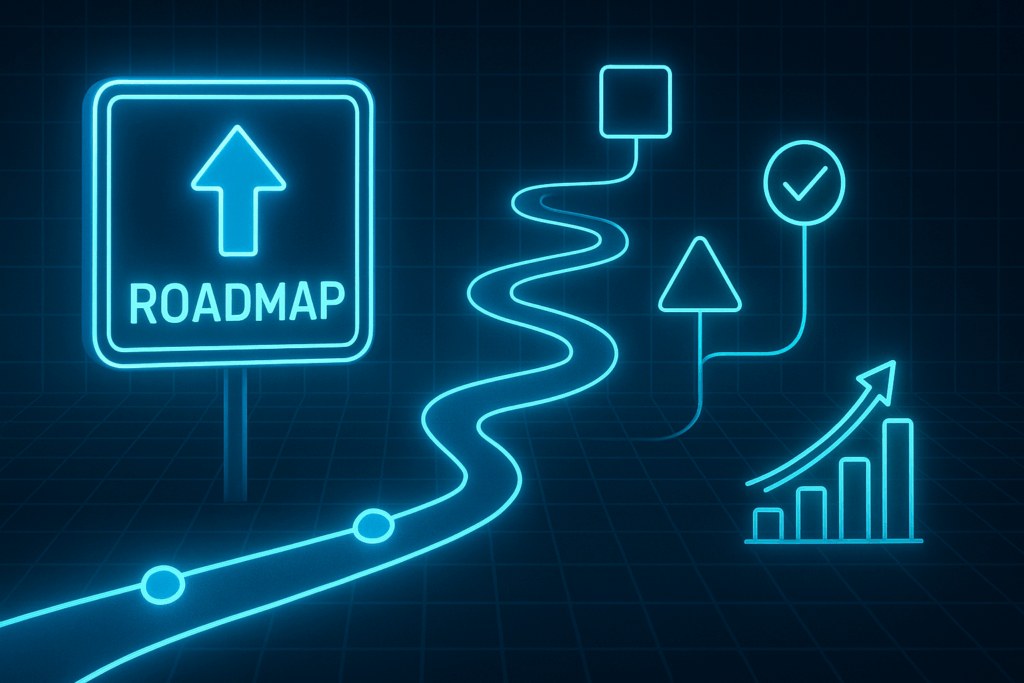
- 2025 Q3:Aristotleメインネット稼働(完了)
- 2025 Q4:Storage SDK v1.0リリース予定
- 2026 H1:Compute層GPUマーケット ベータ公開
- 2026 H2:クロスチェーンブリッジ(BTC・Solana互換)対応
よくある質問(FAQ)
-1-1024x683.png)
-1-1024x683.png)
- 0G(Zero Gravity)とはどのようなプロジェクトですか?
-
0GはAIワークロードをブロックチェーン上で処理できる世界初のレイヤー1です。ストレージ・コンピュート・チェーン・データ可用性の4層構造を持ち、AIとブロックチェーンの融合を実現します。
- 0Gの最大の特徴は何ですか?
-
モジュラー型の設計により、必要な機能だけを選んで利用できる点です。また、EVM互換のためEthereumやPolygon上のdAppが追加開発なしで利用できます。
- どのような資金調達をしていますか?
-
2024年にHack VCやSamsung Nextなどから 4,000万ドルのシード資金 を調達。さらに 2億5,000万ドル相当の流動性枠 を確保し、累計2億9,000万ドル規模に達しています。
- トークン「0G」の用途は何ですか?
-
トークンはガス料、ストレージ報酬、ガバナンス投票、ステーキングに利用されます。ネットワークのセキュリティ確保とインセンティブ設計を両立しています。
- トークンの初期配分はどうなっていますか?
-
エコシステムファンド22%、チーム15%、投資家20%、コミュニティ43%と発表されています。
- 0Gはどの取引所に上場していますか?
-
2025年9月22日に Binance と Kraken に同時上場しました。BinanceではUSDT/USDC/BNB/FDUSD/TRY、KrakenではUSD・EUR建てがサポートされています。
- iNFTとは何ですか?
-
iNFT(Intelligent NFT)は、AIエージェントをNFTに格納する新しい規格です。所有者はNFTの取引と同時に、そのAIエージェントの推論能力も利用できます。
- AIverseとはどのようなサービスですか?
-
AIverseはiNFT専用のマーケットプレイスです。2025年9月にテストネットで公開され、今後の正式版ローンチが期待されています。
- 0Gのリスクにはどのようなものがありますか?
-
競合チェーンとの競争、規制リスク、市場流動性の不足、4層構造ゆえの技術的複雑さなどが挙げられます。投資や開発を行う際はこれらを理解しておく必要があります。
- 今後のロードマップはどうなっていますか?
-
2025年Q4にStorage SDK v1.0、2026年H1にCompute層GPUマーケットのベータ公開、2026年H2にBTC・Solanaとのクロスチェーンブリッジ対応が予定されています。
まとめ


0G(Zero Gravity)は、AIのために設計された革新的なレイヤー1ブロックチェーンです。
モジュラー設計やEVM互換性に加え、iNFTなど独自のユースケースを展開することで、開発者・投資家から強い注目を集めています。
一方で、競合や規制、流動性といったリスクも存在するため、今後の動向を注視する必要があります。
0Gトークンを取引するならBybit(バイビット)がおすすめ!
がおすすめ!-1024x683.png)
がおすすめ!-1024x683.png)
Bybitを選ぶメリット
- ✅ 日本語対応で初心者にも使いやすいUI
- ✅ 取引手数料が安く、スプレッドも狭い
- ✅ 先物・レバレッジ取引など多彩なプロダクトを提供
- ✅ 口座開設は数分で完了、即日トレードが可能
特に0Gのような新規上場銘柄は、流動性が高い取引所での売買が安心です。
👉 今すぐ無料登録して取引をスタートするならこちらから!
おわりに|AI特化型レイヤー1「0G」が切り開く未来





いかがでしたでしょうか?
0G(Zero Gravity)は、AIとブロックチェーンの交差点に立つ革新的なレイヤー1として誕生しました。ストレージからAI推論までをワンストップで提供できる点は、従来のブロックチェーンにはない大きな特徴です。
BinanceやKrakenといった大手取引所への上場、iNFTやAIverseといったユースケースの実装により、その可能性はすでに現実のものとなりつつあります。
しかし同時に、競合チェーンとの開発者獲得競争や規制リスク、市場流動性の課題なども避けては通れません。
これからのAI時代において、0Gがどこまで「インフラ」として定着できるかは、技術の成熟度とエコシステム拡大にかかっています。
投資家も開発者も、常に公式情報をチェックしながら、その成長曲線を見極めることが重要でしょう。
コチラの記事もおススメです。


」とは?仕組みからトークン上場まで徹底解説!.png)


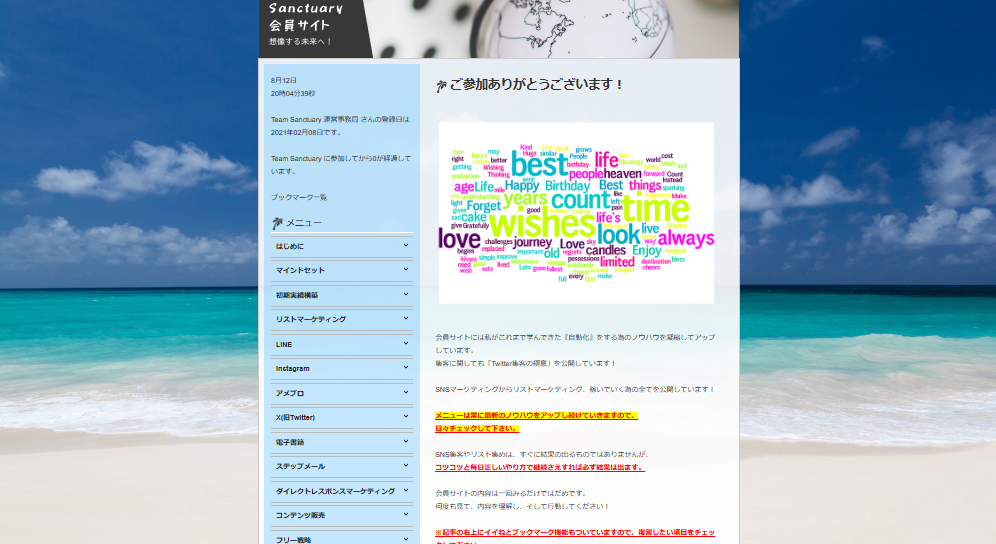
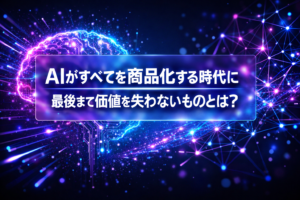





コメント